NEWS


2025.12/09
富士・箱根の社員旅行に行きました!
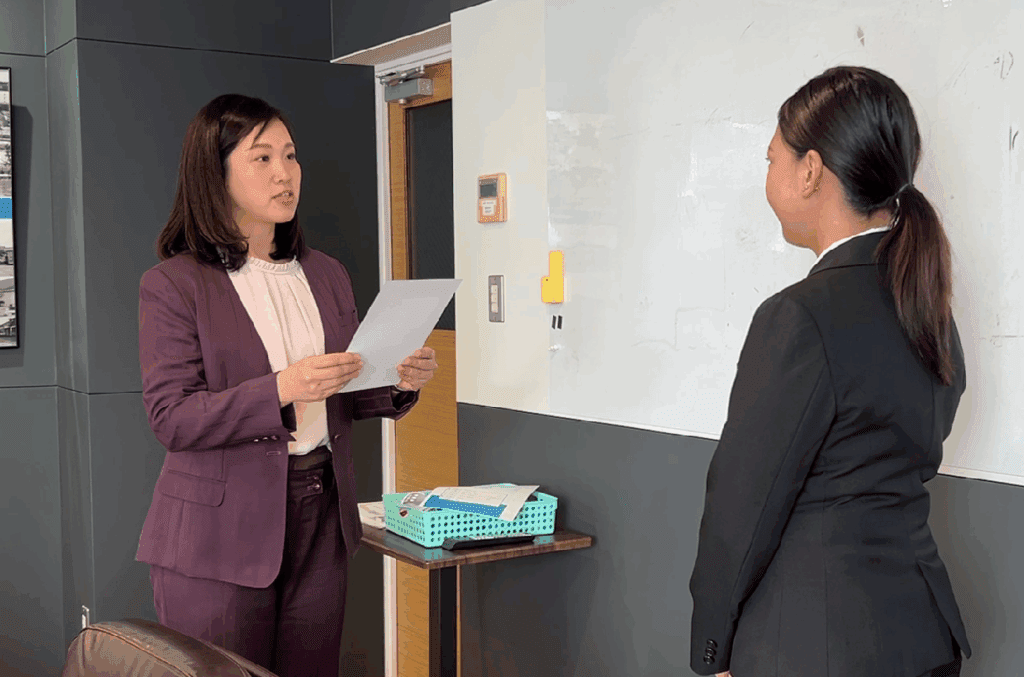
2025.10/22
内定式を行いました!

2025.09/29
社内研修を行いました!

2025.05/30
壁を取っ払い、開放感ある広い事務所に大変身!

2025.05/23
新築社屋の施工紹介動画公開!

2025.04/08


2025.12/09
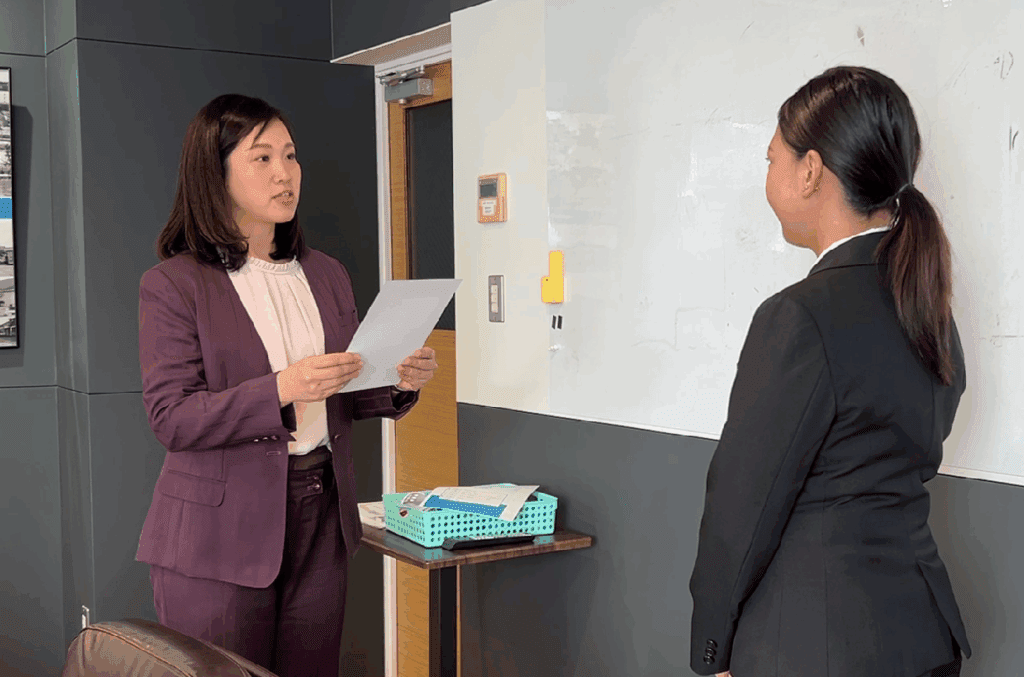
2025.10/22

2025.09/29

2025.05/30

2025.05/23

2025.04/08